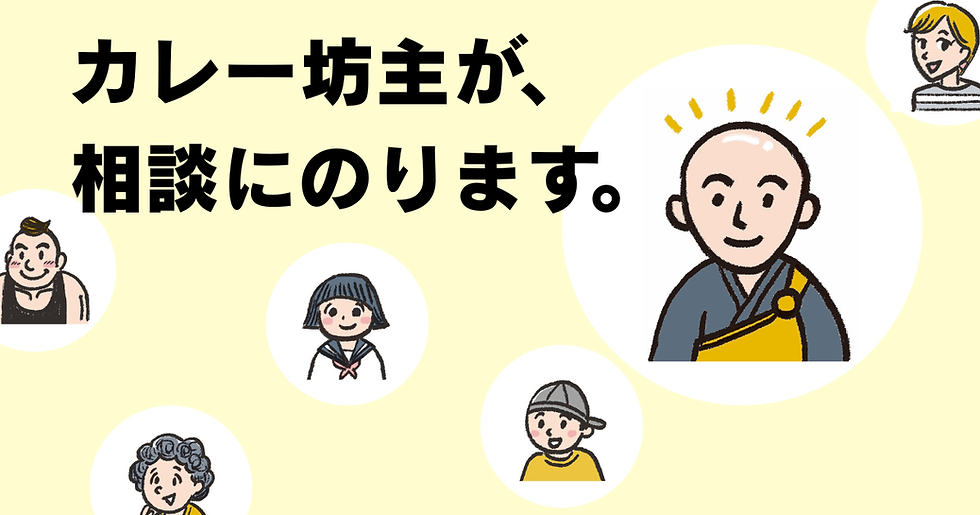遊びの先に見えた技術の未来 東京ゲームショウ発・最新テックレポート
- Oboro Point

- 2025年10月28日
- 読了時間: 7分

先日、幕張メッセで開催された「東京ゲームショウ2025」。会場は例年通りの大混雑で、ゲーム界隈の人気と熱量の高まりを肌で感じました。「バイオハザード」や「サイレントヒル」などの人気シリーズが華やかな展示でゲームファンを迎える一方、AIがゲームプレイの相談役となったり、感情がゲーム演出に反映されたりと、ブースは小規模ながらも最新技術を駆使した“未来を感じる展示”が今年は特に印象的でした。本記事では、そんなゲーム世界の“未知との遭遇”レポート(?)を、ゲーム好きライターのOboro Pointがお届けします。
近未来のゲーム体験を探して
毎年秋になるとやってくるゲームファンのお祭り「東京ゲームショウ」。残暑でぐったりしていても、このイベントを楽しみにしてなんとか乗り切っている人も少なくないはず。
2025年は9月25日から28日の4日間、幕張メッセで開催されました。
今年は47の国と地域から1136の企業・団体が出展。総来場者数も26万3101人と大盛り上がりでした。2026年には史上初の5日間開催も予定されているとのこと。年々スケールアップしていることを実感します。実際に会場は例年通りの大混雑でした。ちなみに私にとってはネットの友人たちと年に一度顔を合わせる同窓会的な場でもあり、まさに全国のゲーム好きが一堂に集まる特別な空間です。

今年は特にeスポーツチームのブースが印象的で、プロゲーマーやストリーマーの人気が確実に高まっているのを感じます。もちろん新作タイトルの試遊や、ゲーム世界をそのまま再現したかのような展示は相変わらず大人気。話題作の試遊にはまるでテーマパークのアトラクションのような行列ができていました。
ただ今回、私が特に目を引かれたのは、そうした派手なブースよりも近未来を予感させてくれる展示ブースでした。
Ovomind:嘘のつけないゲーム体験
まず気になったのが「Ovomindスマートバンド」。腕に装着して心拍やストレスなどの生理的反応をモニターし、プレイヤーの感情をリアルタイムで読み取るデバイスです。

例えばホラーやFPSでは、プレイヤーが緊張すると視界が悪くなるといった演出が可能に。つまり「感情そのものがゲームに影響する」という、これまでにない没入体験が可能になるのです。
ゲームというエンタメの大きな特徴としてインタラクティブ性が挙げられます。小説や映画などほかのエンタメのように作品を受け取るだけでなく、その中にプレイヤーの意思を介入させることができます。これまでは指先の動きなどでそれを行っていましたが、感情フィードバックが加わればさらに「心の動き」までもがゲームに反映されるようになります。
例えば恋愛ゲームで理想通りのかっこいいセリフを選んだとしても、内心ソワソワしていると虚勢がバレてしまい、相手の心を射止められない。自分自身が人として成長しないことには攻略不可能な、クリア率0.001%のヒロイン……そんなゲームが登場するかもしれません。各ストリーマーの配信も大盛り上がりしそう。
他には人狼ゲームで感情メーターが表示される演出も面白そうです。肝の据わった人狼役が平然と人を襲い、緊張しがちな村人にはアラートが鳴りまくる……そんなカオスな展開も想像できます。
その他のジャンルへの応用についても「ゲームという反応速度が求められる場面で有効に機能すれば、ほかのいろいろな分野でも利用できる証明になる」とご説明を受けました。思わず納得。特にマーケティング調査などへの応用が期待されているそうで、アンケートに頼らずユーザーの「反応データ」で見ることができれば、より精確な情報が手に入りそうです。
こちらのプロダクトは朝日新聞やトレたま、書籍『未来をつくる100の技術』などでも取り上げられているようで、まさに注目の最先端技術なんですね。
余談ですが考えているうちに、昔バラエティ番組で見たウソ発見器を思い出しました。結局、技術が進歩しても人間が興味のあることの本質はあまり変わらないのかもしれませんね。
Hakko AI:寄り添うAIゲームコンパニオン
次に紹介したいのがAIゲームコンパニオン「Hakko AI」。大規模視覚言語モデル(VLM)を使ってゲーム画面を読み取り、プレイをサポートしてくれるAIキャラクターです。
対戦ゲームでスーパープレイを決めれば「ナイス!」と褒めてくれたり、ミスをしても優しくフォローも忘れない。ソロプレイでは強敵ボスの攻略法を教えてくれたり、面倒なお使いクエストをサッと調べて案内してくれたりもします。まるでゲーム配信中に視聴者からコメントを貰えるような感覚ですね。

攻略に詰まったときにゲームを一旦中断して調べ出すのは非常に億劫でモチベーションも下がりがちですが、熟練プレイヤーにパッと聞ける環境がいつでもあるのは本当に助かります。個人的には一人で黙々と進めるよりも会話を交えながら遊んだ方が、充実感のある時間が過ごせるように思えます。ついでに「ゲームばかりしていていいのかな…」という罪悪感も薄れ、ゲーム時間をよりポジティブなものとして楽しめること間違いなしです。
どんなゲームにも対応できるそうですが、特別に訓練されたタイトルではより専門的なアドバイスが可能とのこと。現在は6本ほど対応していますが、人気作を中心に順次拡大中だそうです。個人的には「OVERWATCH2」と「Slay the Spire」の対応が待ち遠しいです。

ちなみにこのAIコンパニオンはゲーム以外でも通販サイトでの買い物や、映画・ドラマを一緒に見て感想を言い合うといったことも可能。さらに、視覚・聴覚・会話といったマルチモーダル情報を記憶し続けることができるため、日々の会話から自分専属のコンパニオンとして常に成長していきます。
「褒められて伸びるタイプ」の方は早めに伝えておくといいかもしれません。あるいは「むしろ罵倒されたい」という特殊なタイプにも密かにおススメ……いや、私は全然違いますよ、ホントに。早速感情モニターで確かめるなんて言わないでくださいね。
ハードウェア体験:圧倒的な現実感
もちろん、ハードウェア系の展示も外せません。多種多様な大型デバイスの展示があったのですが特に印象的だったのは、ゲーム画面と連動して動くコクピット型チェアや、本物さながらの操作パネルを備えた兵器シミュレーターです。

フライトシミュレーターは操縦してみると、上空では穏やかでも高度を下げるにつれてマシンの揺れが激しくなり、本当に墜落するのではないかと冷や汗をかくほどでした。厳密には私は飛行機の操縦経験がないので現実通りの表現なのかは分かりかねますが、その「リアルっぽさ」の説得力がなんとも素晴らしいものでした。

見て下さい、この装置の数々を。一体何をどうすればいいのかサッパリ分かりません。プレイヤーは防衛拠点の隊員として、この無数のレバーやダイヤルを指定された順序通りに操作してミサイルを発射しなければなりません。複雑な工程にもたついている間にも敵影はどんどん迫って来ます。慌てて対応しようとするもミスが重なりどんどんパニック状態に…どうやら私には人々を守る責任ある仕事は向いていないようです。特別に発注して制作されたという筐体で行うゲーム体験はまさにここでしか味わえないものでした。
まとめ:未来を感じさせてくれたTGS2025
今回紹介した感情バンドとAIコンパニオン、この2つにも大きな親和性を感じました。AIコンパニオンがプレイヤーの感情をより正確に読み取り、最適なタイミングでアドバイスや励ましをくれる。そこに今回体験したような物理的な演出も加われば、体験は一層深まるはずです。
最新技術が集まる場所に足を運ぶと、その時代ならではの複合的なアイデアが次々と浮かんできます。あらためて、こうしたイベントに参加することの意義を強く感じました。今回のイベントを通じて私は「高度に現実的な非現実体験」が今後のテーマになっていくのではないかと実感しました。AI技術の進歩と並行して、「体験」というコンテンツそのものの需要が高まっているように思います。バーチャルなソフト面での進化と、人間の身体性にフォーカスした製品が組み合わさることで、まるで現実であるかのようにフィクションの世界へ溶け込むことが可能になりそうです。
人混みは相変わらず大変でしたが、まさに言葉通り「遊びきれない無限の遊び場」があったTGS2025。派手な大手ブースももちろん楽しいですが、こうしたユニークで実験的な展示を楽しめるのもこのイベントの醍醐味だと思います。来年の5日間開催ではどんな未来の体験が待っているのか、今から楽しみです。

【執筆者プロフィール】
Oboro Point
器用貧乏に音楽制作やらゲーム制作などに興味を抱いて、最終的には哲学にたどり着く田舎の隠居者。劉玄徳が三度訪ねて来るのを根気よく待ち続けているが、今のところ一度の来訪もない。