【古本屋のリアル③】古本と新本は何が違うの?
- ふじいむつこ

- 2021年9月28日
- 読了時間: 5分
更新日:2021年10月5日
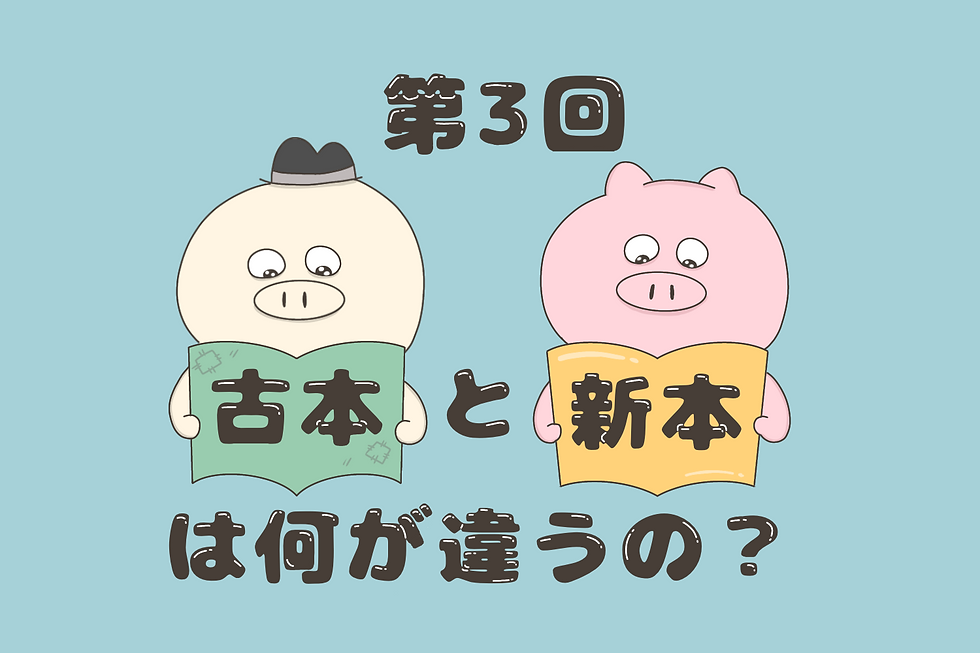
兄の経営する古本屋の日常を妹が描く「古本屋のリアル」。多くの人が「本屋」と言われて思い浮かべるのは、新品の本を取り扱う新刊書店だろう。一方で古本屋は主に「一度、誰かの手に渡った」本を取り扱う。第3回では、そんな新本と古本について描いていただいた。古本には価格以外の魅力がきっとある……?
安いだけが古本の魅力?
自分が手に入れる本はできるだけきれいなものがいい。書店に陳列された本でも、1番上に積まれた本のカバーが折れていたら、下にあるまっさらな1冊を取って買うこともあった。
好きな作家やジャンルなら、なおさら新品のほうがいいと思っていた。もちろんそれはきれいさを求めると同時に、その作家や出版社を応援したいという気持ちもあるからだ。だから古本の良さというものは、ちょっと読んでみたいと思った本や流行りの本が定価より安く手に入る程度の認識だった。
そんな調子だったので、古本好きの人が言う「古本はおもしろい」という意味はわからなかったし、場合によっては新品より高くつく古本を買う気持ちも理解できなかった。カバーは日に焼け茶色く変色していたり、帯が破れていたりする。なぜこんなものをわざわざ買うのだろう。古本よりも古本を好き好んで買う人のほうが、私にはよっぽど興味深かった。
彼らはたいてい仁王立ちで腕組みをし、本棚をじっと見つめている。さながら獲物を狙うハンターだ。レコードをディグるように古写真を掘り起こしている人もいる。その姿がおもしろいので、私も真似して仁王立ちで古本と向き合ってみる。パッと目についた昭和30年ごろに発行された小学館の雑誌を手に取る。極彩色の中でハツラツに笑っているふくよかな子どものイラストを見て思わず「何だこれ」と呟いてしまった。

思えば古本屋は「何だこれ」というものであふれている。赤ペンや蛍光ペンの書き込みだらけの実用書、誰のものともわからぬ旅行の集合写真、バブル時代に建てられたであろう旅館のパンフレット、本の間に挟まれた買い物メモなど……「こんなもの誰がいるんだろう」「何だこれ」の連続なのである。
そしてそんな「何だこれ」との遭遇を期待して、足繁く古本屋に通っている自分がいる。気づけばもうニッチで奇々怪々な古本の沼に足をとられてしまっているのである。
持ってはいないが、古い世界文学全集や日本文学大全集などの全集本の装丁は美しい。独特な幾何学模様、草花を模したようなラインにうっとりする。読み込まれすぎたのか角が溶けたように丸くなってしまった詩集も、それはそれで持ち主にとても愛された証のように感じる。書き込みや開きぐせもあるとうれしい。
「ふむふむ、この人はここがいいと思ったのかな」なんて考えて、本を通して元の持ち主と勝手に繋がった気持ちになることができる。しまいには少し日に焼けているぐらいが味があっていいなんて思っている始末。今ではほこりと湿気が混じったような古本屋独特の香りを嗅ぐだけで胸が高鳴ってしまう。

しかし古本はもろい。そもそも本は丈夫にできているものではない。湿気や水に弱く、かといって日に当たりすぎると変色してしまう。私は特にがさつな人間なのでページをめくったときに力の加減を間違えて折ったり破ったりしてしまうのだが、「こんな力で破れる?」とそのか弱さにうなだれることがしばしばある。

古本ならばさらに気を張る。一見、新本と変わらない見た目をしていても開くとページが抜け落ちそうになっているものがあったり、そもそも背表紙からページ全体が取れかけてしまっていたりするものもあるからだ。
ある日、兄の店で一冊の本を手に取った瞬間、横に立っていた兄に「それ、ほかの店でやったら嫌われるよ」とぴしゃりと言われた。
こちらは本を取っただけだと思っていたから、晴天の霹靂である。どうやら本の抜き出し方に問題があったらしい。私は本の背表紙の上に指を引っ掛けて引き出していた。それは背表紙の折れに繋がってしまう。
ほかにも兄は本を開くときは両手で開くこと、ページをめくるときは指の腹を使って静かにめくるなど事こまかく説明してきた。最初は小うるさく思っていたが、よくよく考えれば商品をていねいに扱うのは当たり前のことだ。
しかし、古本は誰かのお下がりだと思ってしまうせいかその意識が薄れてしまう。すでにカバーが破れていたり、変色してしまったりする本を見ているとなおさら、「古本なんだし、ちょっと雑に扱ってもいいじゃん」と気が緩みそうになる。いくらぼろぼろの本だからといっても店に並べば売り物で財産なのである。だからこそ、古本屋で本に触れるときはそれ以上傷つけてしまわぬようにと、ことさら注意して触れる必要があるのだ。

兄は古本というより、本という存在自体をとても大切にしている。実際、本に触れる手はまるで赤子を抱いているかのようである。たまに愛おしそうに見つめながら撫でていることすらある。さながら本が友達、いや本が恋人なのだ。人一倍本が大切だからこそ、本の触り方にも人一倍厳しい。
閉店後、本棚を整理していて不運にも帯が破れてしまった本を発見した兄は、この世で1番恐ろしい形相で「許さない……」と呟いていた。しかしすぐに「帯が折れてしまうような陳列をしていた自分が悪い」と本当に悲しそうな表情で反省し始めるのである。

そんな兄が身近にいるので、私まで本の扱いが気になるようになってしまった。SNSなどで本を下敷きに花瓶やコーヒーカップを置いている写真を見たときは叫びそうになった。古本屋でも音を立ててページをめくる人や開いたページを下にして屋根のような状態にしている人を見かけると思わず声をかけてしまいそうになる。

今では新刊書店で本を買う際、手に取った本のカバーが多少破れていても気にせずさっと買うようになった。これも味だと感じるからというよりは、ずっと残ってしまうかもしれないその本が気がかりでかわいそうだと思うようになったからだ。これも兄の影響なのだろうか。

ふじいむつこ
1995年生まれ。広島県出身。物心ついた頃からぶたの絵を描く。2020年に都落ちして尾道に移住。現在はカフェでアルバイトしながら、兄の古本屋・弐拾dBを舞台に4コマ漫画を描いている。
Twitter:@mtk_buta
Instagram:@piggy_mtk
◤ あわせて読みたい ◢




